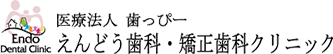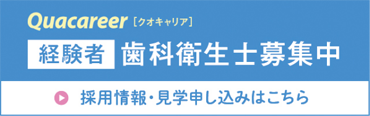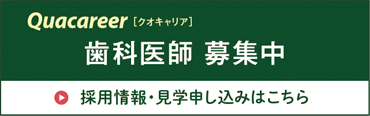唾液の役割について知ってますか?
歯科衛生士の青山です。
今回は唾液のことについてお話していこうと思いますが、
唾液と聞いて何を思い浮かべますか?
 赤ちゃんがよだれを垂らしていたり、ねばねばしているもの、人によっては汚いものと思うかもしれませんね。
しかし唾液と歯の関わりは深く、歯を守っていくのに大切なものなんです。
赤ちゃんがよだれを垂らしていたり、ねばねばしているもの、人によっては汚いものと思うかもしれませんね。
しかし唾液と歯の関わりは深く、歯を守っていくのに大切なものなんです。
 まず唾液がどこからでているかというと耳下腺、顎下腺、舌下腺が大きな開口部(唾液の出口)となっており、耳下腺からさらさらな唾液、顎下腺と舌下腺からはねばねばな唾液と唾液といっても開口部によってでてくる唾液の種類が違います。また、一日に1000ml~1500mlのも量が分泌され、たくさんの働きがあります。
・自浄作用
歯や歯間についた汚れ(食べかすや歯垢)を洗い流す働き
・抗菌作用
唾液の中にペルオキシダーゼやリゾチーム、ラクトフェリンと呼ばれる抗菌物質やIgA、IgGといった抗体が含まれており口の中の細菌の増殖を抑える働き
・pH緩衝作用
食べたり飲んだりするとpHが酸性に傾いてしまうので、唾液の作用で中和させ虫歯を防ぐ働き
・再石灰化作用
pHが傾いたことによって溶けかかった歯を唾液中のカルシウムやリンで歯の表面を再石灰化して虫歯を防ぐ働き
・消化作用
消化酵素(アミラーゼ)の働きで炭水化物(でんぷん)を分解し、消化しやすくする働き
・粘膜保護・潤滑作用
粘液性のムチンが粘膜を保護し、食べ物から守ったり、潤滑油のような働きをしてくれるので発音や咀嚼、嚥下の助けをしてくれたりします
このようなたくさんの働きをしてくれる唾液ですが、全身性の疾患(シェーグレン症候群、更年期障害、糖尿病など)やストレス、加齢、薬の副作用などにより分泌量が減ってしまうことがあります。
そして唾液が減ってしまうことにより、食べ物の飲み込みがしにくくなったり、口の中がねばねばしたり、口を動かしにくくなる、虫歯や歯周病になりやすくなる、口臭が強くなるといった原因にもなります。
もし、最近唾液が減ってきたなと感じことがあれば唾液腺マッサージで唾液の分泌を促すのが効果的です。
方法はまず耳の横を後ろから前に向かって指の腹を使ってゆっくり回します。
次は両手の親指で顎の真下をぐっと押し、下顎の骨の内側を柔らかい部分を骨によって5か所にわけ1―2秒押す。
また、マッサージ以外にもよく噛んで食べたり、小まめに水分補給、鼻呼吸をする、酸っぱいもの(レモンや梅干し)や唾液分泌を促す食べ物を食べたりなど日常生活の中に取り入れる方法もあるのでぜひ試してみてください。
まず唾液がどこからでているかというと耳下腺、顎下腺、舌下腺が大きな開口部(唾液の出口)となっており、耳下腺からさらさらな唾液、顎下腺と舌下腺からはねばねばな唾液と唾液といっても開口部によってでてくる唾液の種類が違います。また、一日に1000ml~1500mlのも量が分泌され、たくさんの働きがあります。
・自浄作用
歯や歯間についた汚れ(食べかすや歯垢)を洗い流す働き
・抗菌作用
唾液の中にペルオキシダーゼやリゾチーム、ラクトフェリンと呼ばれる抗菌物質やIgA、IgGといった抗体が含まれており口の中の細菌の増殖を抑える働き
・pH緩衝作用
食べたり飲んだりするとpHが酸性に傾いてしまうので、唾液の作用で中和させ虫歯を防ぐ働き
・再石灰化作用
pHが傾いたことによって溶けかかった歯を唾液中のカルシウムやリンで歯の表面を再石灰化して虫歯を防ぐ働き
・消化作用
消化酵素(アミラーゼ)の働きで炭水化物(でんぷん)を分解し、消化しやすくする働き
・粘膜保護・潤滑作用
粘液性のムチンが粘膜を保護し、食べ物から守ったり、潤滑油のような働きをしてくれるので発音や咀嚼、嚥下の助けをしてくれたりします
このようなたくさんの働きをしてくれる唾液ですが、全身性の疾患(シェーグレン症候群、更年期障害、糖尿病など)やストレス、加齢、薬の副作用などにより分泌量が減ってしまうことがあります。
そして唾液が減ってしまうことにより、食べ物の飲み込みがしにくくなったり、口の中がねばねばしたり、口を動かしにくくなる、虫歯や歯周病になりやすくなる、口臭が強くなるといった原因にもなります。
もし、最近唾液が減ってきたなと感じことがあれば唾液腺マッサージで唾液の分泌を促すのが効果的です。
方法はまず耳の横を後ろから前に向かって指の腹を使ってゆっくり回します。
次は両手の親指で顎の真下をぐっと押し、下顎の骨の内側を柔らかい部分を骨によって5か所にわけ1―2秒押す。
また、マッサージ以外にもよく噛んで食べたり、小まめに水分補給、鼻呼吸をする、酸っぱいもの(レモンや梅干し)や唾液分泌を促す食べ物を食べたりなど日常生活の中に取り入れる方法もあるのでぜひ試してみてください。
 まず自分でできる対処法を試してみて、それでもなかなか改善が見られない場合にはぜひかかりつけの病院で相談してみてください。
まず自分でできる対処法を試してみて、それでもなかなか改善が見られない場合にはぜひかかりつけの病院で相談してみてください。
 赤ちゃんがよだれを垂らしていたり、ねばねばしているもの、人によっては汚いものと思うかもしれませんね。
しかし唾液と歯の関わりは深く、歯を守っていくのに大切なものなんです。
赤ちゃんがよだれを垂らしていたり、ねばねばしているもの、人によっては汚いものと思うかもしれませんね。
しかし唾液と歯の関わりは深く、歯を守っていくのに大切なものなんです。
 まず唾液がどこからでているかというと耳下腺、顎下腺、舌下腺が大きな開口部(唾液の出口)となっており、耳下腺からさらさらな唾液、顎下腺と舌下腺からはねばねばな唾液と唾液といっても開口部によってでてくる唾液の種類が違います。また、一日に1000ml~1500mlのも量が分泌され、たくさんの働きがあります。
・自浄作用
歯や歯間についた汚れ(食べかすや歯垢)を洗い流す働き
・抗菌作用
唾液の中にペルオキシダーゼやリゾチーム、ラクトフェリンと呼ばれる抗菌物質やIgA、IgGといった抗体が含まれており口の中の細菌の増殖を抑える働き
・pH緩衝作用
食べたり飲んだりするとpHが酸性に傾いてしまうので、唾液の作用で中和させ虫歯を防ぐ働き
・再石灰化作用
pHが傾いたことによって溶けかかった歯を唾液中のカルシウムやリンで歯の表面を再石灰化して虫歯を防ぐ働き
・消化作用
消化酵素(アミラーゼ)の働きで炭水化物(でんぷん)を分解し、消化しやすくする働き
・粘膜保護・潤滑作用
粘液性のムチンが粘膜を保護し、食べ物から守ったり、潤滑油のような働きをしてくれるので発音や咀嚼、嚥下の助けをしてくれたりします
このようなたくさんの働きをしてくれる唾液ですが、全身性の疾患(シェーグレン症候群、更年期障害、糖尿病など)やストレス、加齢、薬の副作用などにより分泌量が減ってしまうことがあります。
そして唾液が減ってしまうことにより、食べ物の飲み込みがしにくくなったり、口の中がねばねばしたり、口を動かしにくくなる、虫歯や歯周病になりやすくなる、口臭が強くなるといった原因にもなります。
もし、最近唾液が減ってきたなと感じことがあれば唾液腺マッサージで唾液の分泌を促すのが効果的です。
方法はまず耳の横を後ろから前に向かって指の腹を使ってゆっくり回します。
次は両手の親指で顎の真下をぐっと押し、下顎の骨の内側を柔らかい部分を骨によって5か所にわけ1―2秒押す。
また、マッサージ以外にもよく噛んで食べたり、小まめに水分補給、鼻呼吸をする、酸っぱいもの(レモンや梅干し)や唾液分泌を促す食べ物を食べたりなど日常生活の中に取り入れる方法もあるのでぜひ試してみてください。
まず唾液がどこからでているかというと耳下腺、顎下腺、舌下腺が大きな開口部(唾液の出口)となっており、耳下腺からさらさらな唾液、顎下腺と舌下腺からはねばねばな唾液と唾液といっても開口部によってでてくる唾液の種類が違います。また、一日に1000ml~1500mlのも量が分泌され、たくさんの働きがあります。
・自浄作用
歯や歯間についた汚れ(食べかすや歯垢)を洗い流す働き
・抗菌作用
唾液の中にペルオキシダーゼやリゾチーム、ラクトフェリンと呼ばれる抗菌物質やIgA、IgGといった抗体が含まれており口の中の細菌の増殖を抑える働き
・pH緩衝作用
食べたり飲んだりするとpHが酸性に傾いてしまうので、唾液の作用で中和させ虫歯を防ぐ働き
・再石灰化作用
pHが傾いたことによって溶けかかった歯を唾液中のカルシウムやリンで歯の表面を再石灰化して虫歯を防ぐ働き
・消化作用
消化酵素(アミラーゼ)の働きで炭水化物(でんぷん)を分解し、消化しやすくする働き
・粘膜保護・潤滑作用
粘液性のムチンが粘膜を保護し、食べ物から守ったり、潤滑油のような働きをしてくれるので発音や咀嚼、嚥下の助けをしてくれたりします
このようなたくさんの働きをしてくれる唾液ですが、全身性の疾患(シェーグレン症候群、更年期障害、糖尿病など)やストレス、加齢、薬の副作用などにより分泌量が減ってしまうことがあります。
そして唾液が減ってしまうことにより、食べ物の飲み込みがしにくくなったり、口の中がねばねばしたり、口を動かしにくくなる、虫歯や歯周病になりやすくなる、口臭が強くなるといった原因にもなります。
もし、最近唾液が減ってきたなと感じことがあれば唾液腺マッサージで唾液の分泌を促すのが効果的です。
方法はまず耳の横を後ろから前に向かって指の腹を使ってゆっくり回します。
次は両手の親指で顎の真下をぐっと押し、下顎の骨の内側を柔らかい部分を骨によって5か所にわけ1―2秒押す。
また、マッサージ以外にもよく噛んで食べたり、小まめに水分補給、鼻呼吸をする、酸っぱいもの(レモンや梅干し)や唾液分泌を促す食べ物を食べたりなど日常生活の中に取り入れる方法もあるのでぜひ試してみてください。
 まず自分でできる対処法を試してみて、それでもなかなか改善が見られない場合にはぜひかかりつけの病院で相談してみてください。
まず自分でできる対処法を試してみて、それでもなかなか改善が見られない場合にはぜひかかりつけの病院で相談してみてください。