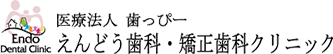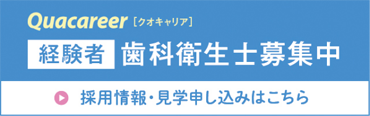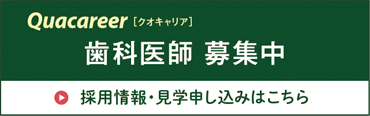よくあるご質問
診療に関するご不安や疑問を解決するために、よくいただくご質問をまとめました。
ご来院前にぜひご確認ください。

ホワイトニングについて
-
全部白い歯になるの?
-
すべての歯が同じように白くなるとは限りません。
ホワイトニングを受ける前に、ご自身の歯がどのように改善する可能性があるか相談してください。 -
一度のホワイトニングで大丈夫?
-
初めての方は、どんなにきれいになっても約1週間で着色してきます。
ホワイトニングは回数を重ねた方がより「白さ」の定着率がよくなります。 -
ホワイトニングは痛くないの?
-
歯のホワイトニングで一時的に「痛み」が出る方がいます。
通常、24時間以内になくなりますので安心してください。
マウスガードについて
-
マウスガードって、どういうものなんですか?
-
スポーツをされている方であれば、一度はお口をぶつけたことがあると思います。
この時口を切る、あるいは歯が折れる、抜けるということがあります。ひどい場合には、あごの骨を折ることもあります。また全体の約7割の方は、思いっきり力を出すときに歯をくいしばっています。
この力により歯がすり減る、歯が割れる、歯を支えている骨がなくなりグラグラになる、といった障害がでることもあります。
このような障害からお口を守るのが「マウスガード」です。
スポーツを愛するすべての人に、マウスガードをお勧めしています。
訪問診療について
-
虫歯や歯周病から命に関わる病気になるというのは本当ですか?
-
口の中は雑菌のかたまりです。
とくに寝たきりなどのお年寄りの場合、口の中の細菌が原因で肺炎を起こすケースが少なくありません。肺炎は高齢者の死因の上位になっていますが、なかでも最も多いのが「誤嚥性肺炎」です。
これは本来食道から胃に入るものや、口腔内の細菌の混じった唾液が、寝ている間に気管から肺に入ってしまうことが原因で起こります。 -
訪問診療はどこで行なわれていますか?
-
歯科医が訪問診療を行っていること自体を知らない方も少なくないようです。訪問歯科診療は、障害や病気による歩行困難や寝たきりの高齢者など、通院が困難な患者さんのための歯科往診サービスです。本人や家族、介護者などの依頼に応じて、歯科医師が自宅、あるいは入院先、特別養護老人ホームなどの施設に歯科機材を運んで、診療を行います。
訪問診療では、一般に歯科医と歯科衛生士、歯科技工士がチームを組んで、虫歯や歯周病の治療、入れ歯作り・調整・修理のほか、介護者へのブラッシング指導、口腔のマッサージ指導、口や舌の運動、咳そう訓練、義歯の調子や口腔状態をチェックする口腔検診なども行います。
訪問診療によって行われる高齢者への歯科治療で、最も大切なのは「口腔ケア」です。口腔ケアというのは、口腔機能を改善するために行う口腔清掃や口腔機能などのリハビリテーションなどを含めたケアのことです。口腔のクリーニングや摂食・嚥下リハビリなどの口腔ケアは、誤嚥性肺炎を防止するためにも大変重要です。脳梗塞の後遺症や痴呆などがある方に対して、口腔への刺激が意識の覚醒にも役立つといわれています。
各自治体に歯科訪問診療を行う歯科医のネットワークもできていますので、訪問診療を受けたいのであれば、県や市の歯科医師会、保健センターなどに問い合わせれば、どこで行っているか教えてくれます。
「日本訪問歯科協会」でも様々な情報を提供しています。訪問診療を依頼する場合には、医療機関に前もって電話連絡をし、患者さんの状況を説明した上で往診日と時間などについて相談してください。
なお、あまり知られていませんが、訪問歯科診療や口腔ケアは各種医療保険のほか、介護保険で受けることができます。
介護保険に入っていなくても、寝たきりの方ならば往診サービスは受けられます。訪問歯科診療は基本的には保険診療が中心になりますが、状態によっては自費での治療が進められるすすめられる場合もあります。 -
寝たきりの人でも受けられる歯科の訪問診療はないのですか?
-
訪問歯科診療を行っている歯科医もいます。近年、お年寄りの歯の健康がその方の生活の質を大きく作用することが認識されるようになりました。「噛む能力」は、ボケ防止にも重要な意味を持っています。口の中の細菌が肺炎の原因になることも指摘されています。
訪問歯科診療では、虫歯や歯周病の治療や入れ歯への対応などの歯科治療はもちろん行いますが、それ以上に大切な役割は、口から食べられるようにサポートすることです。入れ歯が合わない、嚥下障害があるなど、食べられない原因を突き止めて、口腔ケアやリハビリなどによってこれを改善していくわけです。
訪問診療を行う歯科医はまだまだ絶対的に足りません。歯科ユニットを搭載した歯科往診車を持っている歯科医院や歯科医師会などもあります。しかし、残念ながら2002年の健康保険法の改正で、診療報酬が引き下げられ、受診条件が厳しくなったため、訪問歯科診療は多少後退してしまいました。おかしな話ですが、往診に行って家の中で診療するのは認められるけれども、患者さんを往診車に乗せて診療するのはいけないということになったのです。
そんな状況の中で、往診の必要性を強く痛感している一部の歯科医師たちが、ある意味では採算性を度外視して各地で訪問歯科診療に取り組んでいます。
内科的歯科治療について
-
歯周病治療ではなぜ顕微鏡で口の中をチェックするのですか?
-
最近、歯周病治療に内服の抗菌薬(抗生物質)を使う方法が考案されています。私たちの口の中にはミュータンス菌のような虫歯菌や歯周病菌がたくさん住み着いています。その数は約50~100億、種類にして約600種類もあります。とくに歯周病の発症や進行には、特定の嫌気性細菌(空気のないところで生息する菌)が関わっていることが知られています。
歯周病の患者さんの口の中のプラークを取り出し、位相差顕微鏡(口の中の細菌や微生物を生きたまま動き回る状態で、大画面に映し出すことのできる特殊な顕微鏡)で、どのような細菌や真菌が感染しているかを確認します。そして、それらの菌を除去するのに適した抗生物質を飲み、抗真菌シロップでのうがいで歯磨きを行います。
位相差顕微鏡でたくさんの歯周病菌が検出されたら、ジスロマックという抗生物質を使います。この薬は嫌気性菌に対して強い抗菌力を発揮する抗生物質で、細菌を除去すると共にその増殖を抑えます。
これまでの歯周病治療は、歯磨き指導、歯石の除去が中心でした。でも、それだけでは悪い菌を完全に取り除くことはできません。
そうしたいわば外科的な基本ケアに加えて、ときどき位相差顕微鏡で菌の状態を確認し、必要に応じて抗生物質やカビ取り歯磨き剤を併用する内科的治療の2本立てで治療を行うことで、より効果的な歯周病治療ができるようになります。 -
歯周病は薬で治りませんか?
-
歯周病は歯の生活習慣病であり、老化とも考えられます。もしも歯周病が薬で治るとしたら、こんなに素晴らしいことはありません。
歯周病菌を薬で退治する方法として最近注目されているのが、3DS(デンタル・ドラッグ・デリバリー・システム=歯科薬剤到達システム)と呼ばれる治療法です。
歯周病菌にはさまざまな種類がありますが、なかでも最も悪さをする悪玉菌が4種類だといわれています。その4種類が口の中の総細菌数のそれぞれ0.1~0.2%のレベルなら、歯周病を発症しないという研究が報告されています。そうした健康レベルの細菌数に落とすことを目的に行う治療が3DSです。
手順は次のとおりです。
まず、歯型を取ります。その歯形に合わせた樹脂製のマウスピース(ドラッグ・リテーナと呼ばれます)をつくります。その内側に薬を塗って、1日5分間、歯にかぶせて除菌パックをします。マウスピースをはずしてうがいをします。これを一週間続けると、8割方の患者さんで歯周病菌が健康レベルにまで低下し、歯の腫れや出血が治まります。
3DSは本来、PMTCなどの基本的な歯周病治療が終わった後に行う治療です。歯周病治療が終わったら唾液検査をして、歯周病菌の数が健康レベルに達していない場合に3DSが行われます。つまり、唾液検査によって歯周病のリスクを判定し、その人にあった薬剤で化学的に歯周病の進行を防ぐ方法だといえるでしょう。 -
3ミックス-MP法というのはまた別の治療法なのですか?
-
3ミックス法は、虫歯を無菌化する3種類の抗菌薬を混合して行う治療一般のことを指します。
この3種類の抗菌薬は通常内科で使われる内服薬なので粉末です。そのため、患部に効率的に行き届かないという問題がありました。そこで、抗菌薬を歯の中へより効果的に浸透させるために、さらにマクロゴール(M)とプロピレングリコール(P)という2種類の軟膏を加えました。メトロニダゾール、ミノサイクリン、シプロフロキサシンの3剤の抗菌薬とこの2剤の軟膏を混ぜ合わせた治療法のみを「3ミックス-MP法」と呼びます。この治療を確立したのは宮城県の歯科医・宅重豊彦先生です。薬の調剤や保管方法などを厳密に管理し、マニュアルどおりに施行しないと期待する効果はなかなか得られません。薬剤をミックスする量や、歯の中での密閉性などがポイントになります。
宅重先生によると、3ミックス-MP法は単なる虫歯の治療法ではなく、口の中で細菌が原因で起こるほとんどすべての病気を治す治療法だそうです。
この3ミックス-MP法をはじめとする内科的歯科治療のメリットは、麻酔をしなくてもいい、歯を削る量が極端に少ない、痛くない治療ができる、歯の神経(歯髄)を助けられる、抜くような歯を助けられる、歯を長持ちさせるなどが挙げられます。
保険は適用されません。ただし、虫歯治療への有効性・安全性がまだ完全に確立したわけではなく、学会内でもさまざまな論争があります。 -
虫歯に薬を塗って治療できる方法が本当にあるのですか?
-
それは3ミックス(3Mix)法といって、ある意味ではこれまでの歯科医療の常識をくつがえす治療法です。
虫歯の治療は基本的に、「削る」「詰める」「抜く」といった、いわば外科的な処置が中心になります。ところが、この3ミックス法は抗菌薬(抗生物質)によって虫歯の最近を退治する内科的な治療法です。C3の段階(後期の虫歯)でも、神経を残したまま痛みを止めることができます。これは、虫歯におかされた象牙質を削って掻きだし、その穴に3種類の抗生物質を詰めて炎症を抑える方法です。
虫歯は口の中のミュータンス菌などの最近(口腔常在菌)が、食べかすなどから酸をつくって、その酸が歯を溶かすことによってできます。この細菌をやっつけてしまえば、虫歯の進行を抑えることができます。歯にも自然治癒力(自己を修復する力)が備わっていますから、いったん虫歯の進行をストップしてしまえば、やがて元の歯に修復されるはずです。これが、3ミックス法の基本的な考え方です。その方法は次のようなものです。
まず、虫歯の部分に3種類の抗菌薬を塗り、樹脂などでフタをします。このとき、虫歯でどろどろに溶けてしまった部分は取り除きますが、それ以外に歯を削ることはありません。薬剤が浸透すると、象牙質や歯髄(神経)にまで入り込んでしまった菌も殺します。その後、菌の自己回復力でカルシウムが沈着し、約一年後には象牙質の部分が元の状態に戻ります。
3ミックス法なら、これまでは神経を取るしか方法がなかった虫歯でも、神経を残せる可能性があります。なお、この治療法は、本来は内服薬である抗生物質を外用薬として使うので、保険適用にはなりません。 -
歯を削るときの痛みをなくすことはできませんか?
-
最近、某テレビ番組で塗り薬(ペースト)を一回塗るだけで、虫歯が治る治療法があると紹介されました。これはイギリスの科学誌「ネイチャー」で発表された「エナメル質再生法」という治療法で、まだ痛みのない極めて初期の虫歯を治す効果があるといわれ、注目されています。
虫歯は虫歯菌が口の中を酸性にしてエナメル質を溶かすことから始まります。
このペーストはアパタイトと強い酸の溶液を混ぜたもので、これを傷ついたエナメル質部分に塗ると、歯の表面で本物と同じ人工のエナメル質の結晶をさせいさせることができるそうです。ただし、この治療法はまだ厚生労働省の認可を得ていないので、一般の歯科では行われていません。
歯を削らなくてもいい、痛みもない、そんな虫歯治療があれば夢のような話ですが、残念ながら現段階では、虫歯の菌に対する塗り薬や飲み薬は開発の途上にあるというのが実情です。
また、最近では虫歯にレーザー治療を使う試みもなされています。虫歯を削るときにガスレーザー光を照射すると、象牙質が軟らかくなって取り除きやすくなり、しかも痛みもほとんどありません。
口臭治療について
-
自分では口臭が気になるのに他人が気づかないのはなぜですか?
-
口臭には大きく分けて、「他臭症」と「自臭症」があります。他臭症は相手に不快な思いをさせるほどの口臭があるのに、本人は無自覚である場合です。反対に、他覚的には口臭をほとんど認めないのに、本人は口臭があると思い込むケースが他臭症です。
日本における開業医の口臭治療の第一人者である東大阪市の歯科医・本田俊一先生によると、口臭を訴えて受診する患者さんの約8割は自臭症だそうです。本田先生は口臭の原因を大きく次のように分類しています。
一つは中等度以上の歯周病です。二つ目は「歯磨きの回数」に大きく関係があります。歯磨きの回数が多すぎると、口の中のpHを下げるはずの唾液が流されて乾燥してしまいます。この乾燥が問題で、口呼吸によっても口腔内が乾燥してしまいますが、乾燥すると唾液分泌が不足することになります。こうして唾液が少なくなると自浄作用がなくなって、口の中の清潔が保たれなくなり、その結果、口臭が起こります。問題は3つ目の原因です。それは、ストレスです。ストレスによって自律神経が乱れると、やはり唾液の分泌が低下するからです。
自臭症の人は、人前では口を開かなくなるので、口腔内乾燥が起こり、また常に緊張しているために、自律神経が乱れて唾液の分泌がうまくいかなくなります。それがまた、口腔内乾燥を引き起こしてしまい、口臭が起こってしまいます。つまり、「自分に口臭があるのでは…」と思い込んでしまうことで、実際に口臭を招いてしまうという悪循環ができあがるのです。
こうした自臭症の治療は、単なるオーラルケアの指導だけでは十分ではありません。唾液の性状を改善して、口臭そのものを取り除くことに加え、食生活やライフスタイルを改善し、さらに時間をかけたカウンセリングやメンタルケアが必要になります。その上で、患者さん自身が口臭と付き合っていくための生活上の基礎知識などをアドバイスします。生活面でのケアのポイントは、以下のとおりです。まず、歯磨きは起床時と寝る前に行います。食後に歯磨きをすると唾液分泌が低下してしまうので、ブラッシングはせず、ガムを噛むようにします。また、合成界面活性剤を含む市販の歯磨き剤は、使わないほうがよいでしょう。食後や水以外のものを飲んだ後は、必ず水でうがいをします。こまめに水を飲み、口の中のペーハーコントロールをすることが大切です。 -
口臭はどのようにチェックするのですか?
-
口臭というのは心理的な要素もあるので、治療を考えるときはにおいを客観的に分析することが必要です。
以前からあった検査法としては、ガズマトグラフと官能試験が有名です。ガスマトグラフは口臭成分の硫化水素やメルカプタン、揮発性有機酸などがどれだけ含まれるかを調べるものです。官能試験は、歯科医など第三者が鼻で臭気を測定するものです。しかし、それぞれ一長一短がありました。
近年になって、いろいろな口臭診断機器が登場してきました。その一つがアテインという口臭測定器です。検査用の溶剤で口をすすぎ、5分ほど安静にします。溶剤に含まれていた尿素が口内の菌で分解されると、アンモニアが発生します。その濃度を測定して、口臭の強さを調べるのです。
また、ガスマトグラフと同じような方式で、口腔内のガスを検知するオーラルクロマという簡易型測定器も開発されています。これは、口腔内のガスを歯や口腔内に原因があるときに発生するガスである硫化水素、メチルカプタン、字メチルサルファイドの三つに分離します。歯周病であればジメチルサルファイドが多くなるといったように、病気によって増える特有のガスがあるので、口臭の原因を特定できるというものです。
こういった口臭測定器を備える歯科医院も増えてきました。 -
口臭はなぜ発生するのですか?
-
生理的口臭については、唾液自体のにおいであったり歯垢のにおいであったりします。病的口臭については歯科的な問題が主因であったりすることが多いので、きちんと歯周管理をすることが必要です。具体的には「口臭は歯科医院で治せますか?」で触れたとおりです。
その中で食後に口臭が起きる原因としては次の2つのケースが考えられます。
1.食べ残しによってpH(酸性度)が低下し、細菌の酸素活性が高まった
2.食後の唾液が不足している、あるいは唾液自体のpH維持能力が低下した
つまり食べ残しをなくすこと、きちんと唾液が出るようにすることが、食後の口臭対策です。食べ残しは舌の表面、歯ぐきとほほのすき間などの粘膜に潜んでいます。ですから、歯磨きをするより、口に水を含んで口内の上部分を使ってよくうがいするほうが効果的です。食後すぐであれば、水を飲んでも汚くありませんから飲んでしまってください。
また、口臭予防として舌磨きを推奨されることがあります。これは口臭の緩和には役立つと思いますが、実際に清掃できるのは前方だけで、口臭の最大の発生源である舌の奥にまではなかなか届きません。根本的に解決する必要がある場合は、やはり歯科医院でご相談されるといいでしょう。
ただし現在、歯を矯正しているという方は食べ残しが多くなりやすく、口腔内の衛生管理も十分にできないため、口臭が発生しやすくなりますので知っておいてください。
欧米では、二酸化塩素製剤を使ったブレスケアシステムが、一般に広く支持されているようです。根本的解決はさておいて、即効的な効果を期待されるのであれば、市販のタブレット類、消臭スプレー、唾液を分泌させるために梅干などの酸味を使ったアメ類、消臭素材を使用したうがい剤などを利用することも考えられます。 -
口臭は歯科医院で治せますか?
-
口臭には生理的なものと、体に何らかの異常がある病的なものがあります。生理的口臭は誰にでもあるものです。病的口臭には、虫歯、歯周病、歯肉炎などの歯の病気、慢性鼻炎や慢性副鼻腔炎、食道炎、胃炎、胃潰瘍、糖尿病など、いろいろな原因があります。
もし口臭が気になったら、まずは歯科医に相談してみてください。口臭の80%以上は口腔内にトラブルがあることが原因だからです。
最も多いケースは口腔内のプラーク(歯垢)に原因のある口臭です。歯周病が進行すると歯周ポケットから膿が出てきます。これが細菌に分解されると嫌なニオイが発生します。においの元になっているのは、アミンや硫化水素、インドール、メルカプタン、イソ酪酸などの揮発性ガス成分で、歯周ポケットの奥深くに棲息している嫌気性菌(酸素が少ない環境が好きな菌)が作り出しています。
虫歯がたくさんあると、やはり口臭が発生します。神経の腐っている虫歯が1本でもあれば、臭うようになります。舌の根元に付いた白い苔(舌苔)も口臭の原因になります。入れ歯もプラークが付着しやすいので、きちんと清掃しないともちろん口臭の発生源になります。
歯科医院では、防臭と殺菌に効果のあるうがい薬が処方されることもあります。ただしうがい薬はあくまでも対処療法で、これだけで口臭をなくすことはできません。最近は、定期的にクリーニングをするとともに、口腔内にどういう菌があるか、どういうにおいが発生しているかをチェックして、口臭対策を行う歯科医も増えてきています。
口臭予防の基本は、なんといってもブラッシングによるプラークコントロールです。毎食後、就寝前、起床直後にしっかり歯を磨くことが最も大切です。しかし、どれだけしっかり歯磨きをしても歯垢はたまっていきます。歯垢は1~3ヶ月で歯石になります。ですから、少なくとも3ヶ月に1度は歯科医院でクリーニングを行い、歯垢や歯石を完全に取ってください。
また、口呼吸をする人は、口が渇いて細菌が繁殖しやすくなるので、口臭や歯周病の原因になります。くちびるの筋肉のトレーニングを行って鼻呼吸ができるようになると、口臭も改善することがありますし、東洋医学には体質を改善する漢方もあると聞いています。歯科医によく相談してみましょう。
噛み合わせ・入れ歯について
-
噛み合せの治療にはどんな方法がありますか?
-
噛み合わせや顎関節症の治療で最も一般的なのが「スプリント療法」です。保険の適用になっています。
上あごが下あごのどちらかにスプリントというプラスチック製などのマウスピースを装着すると、あごの関節にかかる力の負担が少なくなり、咬合力がそれぞれの歯に均等にかかるようになります。たいていは一ヶ月程度で症状が軽くなります。
マウスピースを入れることで、あごの運動を矯正し、噛み癖を直すこともできます。
スプリントの目的は、筋の緊張を取ると共に、睡眠時のプラキシズム(歯ぎしりや食いしばり)を少なくすることです。歯軋りの習慣のある人には特に効果的です。
原則的に、スプリントを装着するのは夜寝るときだけに限定します。日中や長時間の使用は歯科医の指示に従ってください。
スプリントは口の中に入れるものなので、使用後は水洗いして常に清潔にしておきます。熱湯につけると変形してしまうので、必ず水で洗います。使わないときは水につけて保管します。スプリントをしたまま飲食することはできません。 -
噛むと痛い入れ歯は治りますか?
-
入れ歯を患者さん個々の口の状態に合わせて、最適な条件に設定するのはとても難しいことです。仮の入れ歯のときは口に合っていたのに、完成した入れ歯は当たって痛いということもよくあり、どうしても誤差が生じやすいのです。
どんなに精巧な入れ歯でも、装着直後は多少の違和感や痛みがあります。靴ずれと同じように、歯茎が新しい入れ歯になじむまでは、すれるような箇所が出てきます。ですから、何度か調整して少しずつフィットさせていくことが必要になります。
新しい入れ歯を装着して数日以上経過しても強い違和感があったり、痛みがなくならない場合には、大きく二つの原因が考えられます。まず、口を閉じるだけでも痛ければ、いればと口の中の形が合っていません。かみ締めると痛いという場合は、噛み合わせが狂っていると考えられます。入れ歯が小さすぎても痛みを起こします。
痛みが強い場合は、放置しておいても慣れることはありませんし、傷になることもありますので、入れ歯を外して我慢せずに歯科医を受診するようにしてください。 -
外れやすい入れ歯も治りますか?
-
部分入れ歯の場合、クラスプというバネをかけて支えにする歯には、ヨコの力が加わります。ヨコの力は歯にとって一番苦手なのです。支えになる歯にかかる負担が大きくなっていくと、入れ歯がぐらついたり外れやすくなったりします。
これらの一番の原因はクラスプ(バネ)にありました。金属のバネを使うので異物感が強く、見た目も悪いという欠点もありました。そこで最近ではバネを使わずに安定させるタイプのものがいろいろと考案されています。これらは残念ながらいずれも保険適用ではありませんが、従来の部分入れ歯の短所が改善されて患者さんに喜ばれています。
代表的なものは「アタッチメント義歯」です。残っている歯をかぶせ物で何本か連結させます。その端と義歯をそれぞれアタッチメント(留め金)でホックのようにはめ込みます。バネがないので、口の中がすっきりします。安定性も優れており、着脱が簡単なものも開発されています。
このアタッチメント義歯の留め金、ホックの部分に強力な磁石の力を利用して入れ歯を安定させるのが「磁性アタッチメント義歯」です。残っている歯の根の部分にステンレスを埋め込み、かぶせ物の裏側につけた超小型磁石にくっつけるという仕組みになっています。外れにくい上に取り外しも簡単で、土台にかかるのはタテの力なので、歯への負担が極めて少なくなります。
また特殊な入れ歯としては「コーヌス・テレスコープ義歯」があります。これは、残っている歯にセメントで固定したクラウン(かぶせ物)をかぶせて、その上から人工歯がついている取り外し可能なクラウンを、ちょうどテレスコープ(望遠鏡)のように二重にかぶせてぴったりと固定するというものです。
内側のクラウンと外側のクラウンが、ちょうど茶筒のふたがしっかりと固定するのと同じ原理で入れ歯を安定させます。形は一見、総入れ歯のようになりますが、簡単に着脱できて外れにくく、見た目にもきれいな入れ歯です。
こうして新しく開発されたアタッチメント義歯は従来の部分入れ歯と比べて、食べているときに外れにくく、痛みもないというメリットもあります。しかし最近では、残っている歯をかぶせてしまうより、残っている歯はそのままで歯のないところにインプラントを入れる方が多くなっています。 -
入れ歯は何年くらいもちますか?
-
入れ歯を作ったら一生もつと思っている方もいるようですが、決してそんなことはありません。では、入れ歯の耐用年数はどのくらいなのでしょうか。
これは一概に何年とはいえません。ここの患者さんで口の中の状態が違いますし、いればの設計にも個人差があるからです。
入れ歯を長期間使っていると、人工歯がすり減って、噛み合わせが均等でなくなったり、歳とともに歯槽骨が吸収されて入れ歯が合わなくなったりすることもあります。部分入れ歯では、クラスプをかけている歯に負担がかかって虫歯や歯周病になると、入れ歯が長持ちしなくなります。とくに、手入れの仕方によっては寿命を大幅に短くしてしまいます。
入れ歯を常に口の中に入れたままにしていると、食べ物のカスや歯石などが入れ歯に付着してトラブルの元になります。入れ歯を長持ちさせるには、こまめな手入れが必要です。食事の後は必ず外してきれいに洗わなければなりません。部分入れ歯のバネのかかっている歯はとくに汚れやすいので、寿命が短くなりがちです。入れ歯用のブラシを使って、丹念にブラッシングしてください。通常は水洗いでもかまいませんが、頑固な汚れがあるときは洗浄剤を使います。歯磨き粉には研磨剤が入っているので、入れ歯を傷つけてしまうこともありますから、入れ歯専用の磨き剤を使用してください。とくにプラスチックの部分には菌が住みつきやすく、においの原因にもなるので、なるべくこまめに洗うようにしたいものです。
寝る前にも必ず入れ歯は外しましょう。就寝時は唾液の分泌量が減るので、入れたままにしておくと汚れがつきやすくなり、入れ歯が長持ちしません。外した入れ歯をそのまま放置しておくと、乾燥して入れ歯が変形したり、ひびが入ったりします。きれいに磨いて入れ歯洗浄剤に浸けて保管します。 -
どこまで小さな入れ歯にすることが可能ですか?
-
患者さんの希望で一番多いのが、「小さい入れ歯を作ってください」ということです。しかし逆に、私たち歯科医は将来的にも安定して使えるように、なるべく大きな入れ歯を作ろうとします。
なぜかというと、ぐっと噛むときというのは、体重と同じくらいの力がかかります。健康な歯であればその力を歯で支えることができますが、入れ歯になると歯のかわりに歯茎の粘膜で支えることになります。そのときに小さな入れ歯では噛む力を受け止めきれません。小さい入れ歯にすればするほど一点に力がかかるので、噛むときに痛みが伴いやすくなります。噛む力を分散させるためには、床の面積を広くして、強い力でも受け止めることのできる大きな入れ歯が必要なのです。
使う立場からすれば、入れ歯は小さいに越したことはありません。できれば入れたくないわけですから、もちろん患者さんの希望に沿ってなるべく小さくしてあげたいと思います。しかし、限界があります。そこを理解していただきたいのです。
きちんと設計された入れ歯は、大きさを感じないものです。大きな入れ歯が気持ち悪く感じるのは、むしろ噛み合わせが低すぎることや、床の厚みが合っていないことが原因になることも少なくありません。入れ歯が大きいと感じて違和感があるときは、歯科医院で装着状態をチェックして、少しずつ調整してもらってください。ほんの少し削ったり調整しただけで、案外気にならなくなるものです。
患者さんの希望で一番多いのが、「小さい入れ歯を作ってください」ということです。しかし逆に、私たち歯科医は将来的にも安定して使えるように、なるべく大きな入れ歯を作ろうとします。
なぜかというと、ぐっと噛むときというのは、体重と同じくらいの力がかかります。健康な歯であればその力を歯で支えることができますが、入れ歯になると歯のかわりに歯茎の粘膜で支えることになります。そのときに小さな入れ歯では噛む力を受け止めきれません。小さい入れ歯にすればするほど一点に力がかかるので、噛むときに痛みが伴いやすくなります。噛む力を分散させるためには、床の面積を広くして、強い力でも受け止めることのできる大きな入れ歯が必要なのです。
使う立場からすれば、入れ歯は小さいに越したことはありません。できれば入れたくないわけですから、もちろん患者さんの希望に沿ってなるべく小さくしてあげたいと思います。しかし、限界があります。そこを理解していただきたいのです。
きちんと設計された入れ歯は、大きさを感じないものです。大きな入れ歯が気持ち悪く感じるのは、むしろ噛み合わせが低すぎることや、床の厚みが合っていないことが原因になることも少なくありません。入れ歯が大きいと感じて違和感があるときは、歯科医院で装着状態をチェックして、少しずつ調整してもらってください。ほんの少し削ったり調整しただけで、案外気にならなくなるものです。
妊娠・出産との関係について
-
矯正期間中に妊娠しても大丈夫ですか?
-
矯正治療の期間は長くかかりますので、その間に結婚や妊娠を経験される方もいらっしゃると思います。そこで心配になるのが、矯正治療期間中の妊娠や出産ですが、特に問題はありません。
ただ、妊娠が分かったら歯科医師に伝えていただければと思います。時期によってはレントゲン検査や抜歯などの治療を避けたほうが良い場合もありますので、事前に分かれば、検査や治療の時期をずらすこともできます。
また、妊娠初期になるとつわりがあり、大きく口を開けることがつらいことがあるかもしれません。そうした場合は、治療を一時的に中断する場合もあります。 -
妊娠中は虫歯や歯周病になりやすいと聞いたのですが、本当ですか?
-
本当です。妊娠中につわりなどがある場合、歯ブラシを口に入れたりしただけで気持ちが悪くなってしまい、ハミガキをしづらくなります。そのため、ハミガキがおろそかになりやすく、虫歯や歯周病になりやすいといえます。
また、妊娠すると増える女性ホルモンを利用して細菌が増殖し、歯周組織の炎症が起こる場合もあります。
健康な歯を守るため、妊娠中も定期的に検診されることをオススメします。
歯ぎしりについて
-
歯ぎしりするのですが、放っておいても大丈夫?
-
歯ぎしりをするときにはとても強い力が働きます。
そのため、歯の表面がすり減ったり、時には歯が欠けたりすることもあります。歯根の部分にも大きな影響を及ぼします。
そうなる前に、家族などから歯ぎしりを指摘される方、朝起きたときにアゴや歯に違和感のある方は歯科医師のチェックを受けてください。
歯について
-
なぜ定期的な検診が必要なのですか?
-
毎日使う口の中に歯垢がたまったり、義歯の不具合がおこったり、危険がいっぱい。
この為、定期的に歯医者に異常がないか見てもらいましょう。
臼歯(奥歯)には40~60kg、前歯で20~30kg、毎日負担がかかっています! -
寝かせ磨きを上手にするにはどうしたらよいのでしょうか?
-
お母さんのひざの上に赤ちゃんの頭をあお向けにのせて、アーンと口をあけてもらいます。
よくお話しをしながら、はじめはおあそびのつもりでソフトタッチでスタートします。左手で口びるを充分よけ、歯をよく見ながら順序よくみがくのがコツです。 -
指しゃぶりをなかなかやめられません。歯並びに悪いと聞いていますが?
-
昔は何か欲求不満があるために指しゃぶりをすると言われていましたが、今では単なるくせといわれています。
前歯が咬み合わないなどの悪い影響は、1才半をすぎるとでてきますので、そのような場合はできるだけ早くやめるよう、根気よく努力してください。 -
歯医者さんでの定期検診はどのくらいおきに行ったらよいでしょうか?
-
だいたいの目やすは3~6カ月おきでよいのですが、年令の低い場合やむし歯にかかりやすいタイプの子は3~4カ月おきに、むし歯にかかりにくいタイプの場合は5~6カ月おきでよいでしょう。
乳歯や六才臼歯の進行は思ったより早いものなのです。 -
乳歯の前歯の噛み合わせが反対なのですが、どうしたらよいでしょうか?
-
奥歯がはえる前の1才台での反対は、奥歯で咬むようになると治る場合もありますが、乳歯がはえそろた段階での反対は自然には治りません。
早く治した方が良いという説もありますが、一般的には上下4本がはえ変わってから一度、歯医者さんに相談してください。
歯科医院について
-
歯科での漢方はどんな疾患に効果があるのですか?
-
1983年に発足した日本歯科東洋医学会では、「全身の状態が口腔に投影される」という東洋伝統医学の教えを礎に活発な活動を展開しており、数多くの臨床例が報告されています。
その中で具体的に期待されているものでは、まず直接口腔内患部に塗布する外用として「止血と痛みの緩和」「歯茎の腫瘍・口腔ガン・歯周病・歯槽膿漏」などがあげられます。一方、患者さんが飲む内服では「肝臓の働きを改善することによる口臭の解消」「歯茎や口腔ガンの改善」「血の改善による歯槽膿漏の治療」などが注目されています。
歯科医院では当然、口腔内診察が不可欠ですから、「舌診」をするのは極めて自然です。つまり歯科医が例えば舌の色、舌の形、苔の色、苔の形から診断可能になるだけでも、歯周病やドライマウス、口臭症、口腔内粘膜疾患、三叉神経痛など、あらゆる疾患に対応できるというわけです。
現状では、漢方を臨床に応用している最先端歯垢の歯科医院は、熱い注目を浴びているとはいえ、それほど多くありません。日頃から漢方薬を使用している方は、歯科医に伝えるといいでしょう。 -
歯科でも漢方を導入しているところがあるのですか?
-
そもそも漢方は私たち日本人にとってなじみが深く、特に高齢の患者さんの中には日常的に使っている方も少なくありません。ですから私は、歯科医に限らず医療従事者は、基本的知識として漢方の考え方を知っておく必要性があると考えています。
とはいうものの、実際に歯科で漢方または漢方薬を導入している医院はまだ少数で、最先端の治療と言えるでしょう。その意味やメリットについても知られていないのが現実です。
漢方には様々なメリットがありますが、私の長年の臨床経験から補足すれば、漢方は口臭解消のために体質改善が必要と思われる方や、高齢者や子どもにとって優しい治療法だと感じています。 -
よい歯科医の条件とはなんですか?
-
歯科治療は日々進歩しています。医療機器や素材など、特に最近の技術革新にはめざましいものがあります。あなたの通っている歯科医は、こうした進歩した技術を積極的に学び、診療室での治療に的確に生かしているでしょうか。
これは、よい歯科医の第一条件だと思います。同じ虫歯でも、歯の状態によって治療方法は様々です。治療技術の良し悪しを判断するのは患者さんにとってなかなか難しいですが、たくさんの治療メニューを提示してくれるかどうかは、一つの目安になるでしょう。
そしてインフォームド・コンセント(医師の説明と患者の同意)が十分に行われているか、院内が清潔であり、スタッフがにこやかでてきぱきと対応しているか、予約制であっても急な痛みで受診した場合にはきちんと対応してくれるかどうかも基準になります。
さらに、予防治療が重視されている現在の状況をきちんと認識し、歯ブラシ指導をしっかりと行っているか、かみ合わせに十分気を配っているか。こうした点にも注目していきましょう。
逆に、最初から高額の治療費の話をする歯科医は避けたほうが無難です。
いずれにしても、患者さんに対して誠実に対応しているかどうかは、態度や雰囲気から自然とにじみ出てくるものです。
ただし、これはあくまでも一般論です。個々の患者さんと個々の歯科医の相性が合うかどうか。最終的にはやはりそこに行き着くのではないでしょうか。 -
自費診療の歯は保険診療より長持ちしますか?
-
「保険診療では十分な治療ができません。少し高くなりますが、自費ならば長持ちする治療が可能です。」といわれたことがあると思います。
もしやこの歯科医は金儲けのために保険外治療をすすめているのでは…?ちらりとそんな疑念がよぎってしまうこともあるでしょう。しかし、ほとんどの良心的な歯科医は金儲けのために自費治療をすすめているのではなく、治療上やむをえない場合が多いのです。
これはまさに治療ゴールの問題です。一概に保険は悪い、自費がよいという話ではありません。保険の歯でもそれなりに長持ちします。ですが、自費の歯は強度もありますし、変色しにくいというメリットがあります。どこで手を打つかは患者さん自身がゴールをどこにおくかという問題です。じっくり考えて判断していただくしかありません。
高額の費用がかかったからといって、レベルが高い治療だとは必ずしもいえません。診療費が高くついても、より快適で長持ちするものを選ぶか、保険診療の範囲で満足するかは、個々の患者さんの価値観によります。いずれにしても、きちんと医師の説明を求めて予算を検討し、納得したうえで治療をスタートすることが大切です。 -
保険診療と自費診療はどう違うのですか?
-
歯の治療には「保険診療」と「自費診療(保険外診療)」があります。保険診療は健康保険が適用されるので、患者さんは一部の負担金を払えば治療が受けられますが、自由診療は保険がきかないので、全額自己負担になります。一般的な歯科は保険診療と自費診療の両方を行います。保険診療は全国どこでも一律料金ですが、自費診療は歯科医院によって設定料金が違います。
虫歯や歯周病、入れ歯などの一般歯科治療、検査、口腔外科的治療には保険が適用されます。
保険と自費の違いは、基本的に治療内容と、かぶせ物や詰め物の素材の違いです。例えば、保険では奥歯にかぶせるのは金属になります。前歯は白いかぶせ物も可能ですが、材質がプラスチックなので変色しやすくなります。ただし、セラミックの詰め物やゴールドなど、質のよいものを望めば自費になります。
通常必要な治療は保険診療の範囲ですべてできる。これが保険制度上の建前です。しかし、限られた枠の中では不可能な治療があるのも事実です。例えば、インプラント(人工歯根)のような特殊な治療には保険は適用されません。
一般に、「悪くなってしまった歯を最低限悪くない状態にする」というのが保険診療です。しかし、歯科医療の分野では審美的な治療も多いので、保険では受けられない診療行為が多くなっています。
歯科医療の技術は日進月歩で進歩しています。その高度な技術や材料をすぐに保険適用にするには、健康保険の財政上どうしても無理があるのです。
治療費・保険について
-
自費の治療は一生もつものですか?
-
自費、保険の治療の区別なく、定期的な検診を行わないのであれば、治療の効果はありません。
痛みについて
-
矯正治療は痛いと聞いたのですが本当ですか?
-
たしかに痛みを伴う場合がありますが、それでも短期間でなくなるため、問題になることはほとんどありません。矯正治療によって初めて装置を口の中に入れて4~5時間位で歯が動く準備をはじめます。
そのときに個人差はありますが歯が浮くような違和感、噛んだときに痛みを生じるなどの症状が現れることがあります。個人差がありますので、最初からほとんど違和感さえない方、長く1週間くらい続いてしまう方もいますが、通常は2、3日で治ることが多いようです。
矯正治療について
-
アライナーの違和感はどのくらいで慣れますか?
-
アライナーを交換した初日が最も違和感が生じます。通常2~3日程度で慣れます。違和感が強い場合には、交換は就寝前にすると良いでしょう。歯の移動中には、歯の軽い痛みや知覚過敏症状が起こることがありますが、これも一時的なことが多いので心配はありません。
-
20時間装着できなかった場合はどうすればいいですか?
-
アライナーは20時間装着することで、計画通り安全に歯が移動します。頻繁に20時間使用できない場合は、治療を中止せざるを得ない場合もあります。
まずは20時間使用する習慣をつけてください。20時間装着できない場合は、無理にスケジュール通りに交換せず、ドクターに相談してください。 -
歯が動くのを実感するまでどのくらいですか?
-
治療計画は、それぞれ異なります。歯の移動するタイミングや方向も個人差がありますので、歯が移動するのを実感するのにも個人差があります。
-
歯のクリーニングはしてもいいの?
-
当医院では、アライナーの交換時期にクリーニングを行っております。それ以外のタイミングでクリーニングを希望される場合は、別途料金がかかります。
-
かみ合わせに違和感があるのですが
-
矯正治療中は、奥歯のかみ合わせが変わります。それによって、かみ合わせの違和感や顎に疲れや痛みを感じることがあります。ほとんどの場合、一時的なことが多いので、アライナーを装着して治療を続けましょう。
虫歯・歯周病について
-
進行した歯周病でも治療できますか?
-
進行した歯周病に対しては外科的治療を行うのが一般的です。最もよく行われるのは病的な歯肉を切除する「歯肉剥離掻爬手術(フラップ手術)」です。進行した歯周病の部位の歯肉をはがして歯根を露出させ、歯根の表面についている歯石や細菌を取り除いて、さらに歯肉と歯槽骨を整形する手術です。手術といっても痛みはほとんどありません。
新しい技術としては、歯周組織を再生させる「歯周組織再生誘導法(GTR)」という手術があります。
歯周病で失われた歯槽骨がコラーゲンなどの特殊な膜を使って再生されるので、以前であれば抜歯するしか方法がなかったケースでも歯を残すことができるようになりました。また現在では、歯槽骨を作るためにエムドゲインという薬剤を塗る方法もあります。歯周病が進行して膿ができているようなときは、テトラサイクリン系などの抗生物質を歯周ポケットの奥に入れる薬物治療も広く行われています。麻酔をしてメスで切開し、抗生物質を注入します。
歯茎に腫れや痛みがある場合、うがい薬や消毒剤で、歯周ポケット内を直接洗い流す「ポケット内洗浄法」も有効といわれます。
歯周病に対するレーザー治療も一般的になりつつあります。とくに炭酸ガスレーザーは歯周ポケットの細菌を減らし、炎症を起こしている組織を焼き取るのに効果的です。レーザー治療によって弱っていた歯肉の血行を改善するため、歯周病の再発率が低いといわれています。また、レーザーで歯石を除去すると、プラークや歯石が付着しにくくなるとも考えられています。
しかし、どうしても歯を残せないほど歯周病が進行している場合には、骨の吸収を抑えるとともに他の歯への炎症を食い止めるためにも、早めに抜歯したほうがよいでしょう。 -
歯周病を予防するにはどうすればよいですか?
-
毎日のブラッシングなどのお手入れはもちろん大事ですが、それだけでなく定期的に歯科医院に通って口の中のクリーニングをすることが必要です。デンタルケアは「現在の状態をさらによくすることで歯の病気を予防する」という考え方が主流になっています。
その考え方に基づいて行われるのが「PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)」です。これは「歯科医院で行われる専用機器を使った専門家による徹底的な口腔内クリーニング」のことです。
専門家によるブラッシング機器を使ったプラークコントロールは、PTC(プロフェッショナル・トゥース・クリーニング)と呼ばれます。これはすべての歯面からプラークを取り除くためのクリーニングで、ブラシを使って行われます。
これに対してPMTCは、ブラッシングでは難しい歯と歯の間や付け根などにも研磨剤を入れて、ブラシやゴムを高速回転させて行うクリーニングです。スケーラーによる歯石除去、歯周ポケットも十分洗浄した上で、仕上げに虫歯予防のためにフッ素化合物を塗ります。
なお、PTCは保険適用ですが、PMTCは自費になります。費用は、1回30分~1時間で3千~1万円程度です。こうしたプロフェッショナルによるクリーニングを定期的に行うことで、歯の健康を長く保つことができます。歯周病の方は、3ヶ月に1回、それ以外の方は3ヶ月から1年に1回のペースでクリーニングを受けることをおすすめします。 -
歯石とは何ですか?
-
歯周ポケットの中にたまった「プラーク(歯垢)」が、長い間、歯についたままになっていると、このプラークに唾液の中に含まれているリン酸カルシウムなどが付着し、石灰化して硬くなります。これが「歯石」です。細菌の巣のようなものです。プラークは2週間で歯石に変化します。
ですから、プラークがまだ歯石に変わる前に、しっかりと除去するようにしたいものです。プラークは粘着性が強く、水にも溶けないので、ブラッシングで取り除かなければなりません。
歯石は虫歯の原因にはなりませんが、歯周病の原因の一つです。歯石の表面はザラザラしているので、プラークがつきやすい状態になっており、放置すると歯石はさらに厚く硬くなっていきます。これが歯肉を刺激して炎症を悪化させるという悪循環になります。
歯石は古くなると、石灰化が強くなって取り除きにくくなります。また、歯肉の内側の深いところに向かって作られていきます。歯肉の縁より下にできる歯石は肉眼では確認できず、見えるところにできる歯石よりも硬くてとりにくいので、より注意が必要です。 -
歯周病になるとどうなりますか?
-
歯周病は次のようなステップで症状が進んでいきます。見て分かるように、症状が進むと大切な歯を失うことになりますので、注意が必要です。
1.歯を磨くと血が出る
2.ときどき歯肉が腫れる
3.口臭が出る
4.歯が長くなったように見える
5.歯と歯の間にすき間ができて、食べ物が入りやすくなる
6.歯が動くようになり、よく噛めなくなる
7.歯がグラグラになり、やがて抜けてしまう
これを歯周病の重症度に分けて説明すると、次のようになります。
●歯肉炎
歯と歯茎のすき間にプラークが溜まり、歯肉に炎症が起こって赤く腫れて歯周ポケットになります。プラークはやがて石灰化して歯石になり、ここではまだ骨の吸収はありません。
●軽度歯周炎
歯周ポケットが深くなり、細菌が増えてきて炎症は進みます。歯の周りの歯槽骨が吸収され、歯を支えている周りの組織がじわじわと壊されていきます。
●中等度歯周炎
さらに炎症が悪化して歯槽骨は破壊され、歯がグラついてきます。
●重度歯周炎
歯の根の半分近くまで歯槽骨が壊されて歯がグラグラになった状態。すでに手遅れで、まもなく歯は抜けてしまいます。
歯周病がどのくらい進行しているかを知る目安は「歯周ポケット」の深さです。歯周ポケットの深さは、健康な歯茎では1~2ミリですが、中程度の歯周炎があると3~5ミリになり、進行すると6ミリ以上になることもあります。歯周ポケットの中にたまったプラークでは細菌は繁殖しやすく、硬くてブラッシングでは取り除けない歯石ができて、歯茎の炎症はどんどん進んでいきます。その結果、歯を支える歯槽骨を溶かしてしまいます。
歯周病は冠動脈疾患の発症率を上げるという報告もあり、心臓病や糖尿病などをはじめとするさまざまな全身疾患に影響を与えると考えられています。 -
なぜ歯周病になるのですか?
-
「歯周病」は、歯茎に起きる可能性の炎症です。昔から俗に「歯槽膿漏」と呼ばれていました。45~55歳代の日本人の約90%がかかっているという国民病です。
意外に思われるかもしれませんが、歯周病は虫歯と同じように口の中の最近によって引き起こされる感染症です。その原因は歯の汚れ、「プラーク(歯垢)」です。プラークは歯の表面や、歯と歯の間にある白くてネバネバしたものですが、これは食べ物のカスではありません。その80%以上は虫歯菌や歯周病菌など細菌のかたまりです。口の中には300種類の細菌がいますが、このうち10種類程度が歯周病を悪化させることが分かっています。
歯と歯茎のすき間(歯肉溝というミゾ)にプラークが溜まると、その中にいるバクテリアが約24時間かけて繁殖していきます。このバクテリアの出す毒素が歯肉に炎症を起こし、化膿していきます。こうして歯周病が始まるので、歯肉が炎症で腫れてくるとミゾが深くなり、ポケットができます。これが「歯周ポケット」です。汚れが入り込むことからポケットと呼ばれています。そこでは歯周病菌はさらに増殖します。プラークはやがて石灰化して「歯石」となり、歯周病は悪化していきます。ひどくなると骨が溶けてしまいます。
歯周病は中高年の人が圧倒的に多いのですが、お菓子や清涼飲料など糖分を取りすぎる子どもにも多く見られます。若いときから徐々に進行していきます。高齢者に多いため、老化現象のように考えられていますが、丹念な歯磨きによるプラークコントロールと、PTC、PMTCといった歯科医での専門的なクリーニングを定期的に行うことで、実はほとんどの歯周病は予防できます。とくに糖尿病などの全身疾患がある方は、歯周病はより早く進行しますので、きちんとメンテナンスしましょう。
予防歯科について
-
キシリトールとフッ素の違いは何ですか?
-
最近、キシリトール入りのガムや食品がたくさん売られています。キシリトールは虫歯予防効果が実証されている天然の甘味料で、主に北欧で20年ほど前から虫歯予防に使われてきました。
キシリトールは、白樺や樫の樹木からとれるキシラン・ヘミセルロースという糖分から作られています。虫歯は、ミュータンス菌などの虫歯菌が糖分をとって酸を発生することがきっかけで作られますが、キシラン・ヘミセルロースは他の糖とは違い、ミュータンス菌に食べられても酸を作りません。プラークを減らし、ミュータンス菌の働きを弱め、虫歯になりかかった歯のエナメル質を再生し、またプラークの中にカルシウムを取り入れる働きもあるので、歯の再石灰化も促進されると考えられています。虫歯予防を期待する場合、キシリトールは1日5~10グラム程度(100%キシリトールガムで約5枚)を数回に分けて、食後に摂取するのが適当と考えられています。
注意点として、キシリトール入りの商品には他の甘味料も多く使われている場合があります。「砂糖」「水あめ」といった表記のあるものは虫歯を作り出す砂糖が含まれているので、歯磨きの後や寝る前に食べることは避けましょう。
一方フッ素は、鉄やカルシウムのように自然の中にある微量元素(ミネラル)です。緑茶や紅茶、海藻類、魚介類などに多く含まれ、歯や骨を丈夫にする栄養素です。歯質を強くし、プラークの生成を抑え、歯の再石灰化を進めるなどの虫歯予防効果が認められており、フッ素液を直接塗ったりスプレーしたり、フッ素入りの歯磨き粉やうがい薬として使うことが推奨されています。アメリカの州によっては、水道水にも加えられています。
フッ素は歯自体を丈夫にできるので、キシリトール以上の虫歯予防効果を期待できます。特に子供の虫歯予防に役立つといわれています。ただし、プラークを取り除いてくれるわけではありません。
繰り返しますが、プラークは歯ブラシなどでかき出さなければ決して取り除けません。キシリトールやフッ素を使えば、虫歯にも歯周病にもならないと考えるのは大きな間違いです。あくまでも歯磨きをサポートするものだと考えておきましょう。 -
歯科医院でもフッ素塗布をしてもらえますか?
-
もちろんです。歯科が行うフッ素クリーニングとは、一般に歯科医や歯科衛生士がさまざまな器具やフッ素入りペーストなどを使って、歯とその周囲のプラークを取り除く処置です。とくに、虫歯や歯周病菌が集まって歯の表面にできる「細菌バイオフィルム」は、通常の歯磨きではなかなか取り除けませんが、これをはがし取るのにフッ素クリーニングは効果があります。
フッ素を使った虫歯予防処置はいくつかの方法があります。
最も一般的なプロフェッショナルケアとして歯科医院で行われるのは、歯冠の表面にジェル状のフッ素化合物を塗る方法です。
PMTCなど専門的なクリーニングを受けると、仕上げにフッ素を塗布します。また歯周病の治療でも、歯根の保護にフッ素を使います。そのほか、微弱電流機を用いて、フッ素を歯冠からエナメル質内部に浸透させる「イオン導入法」という方法もあります。ちなみに、フッ素の効果がより発揮されるのは生えて間もない永久歯に対してです。ですから、学童期の対応がいちばん重要になります。
ただし、歯科医院などでフッ素による予防処置を一度受けたからといって、その効果が長続きするわけではありません。定期的な受診と、フッ素の添加されている歯磨き剤やスプレー、うがい剤を使ったホームケアも大切になります。 -
フッ素で虫歯が予防できるというのは本当ですか?
-
フッ素の虫歯予防効果については、世界保健機関(WHO)などの専門機関がその有効性と安全性を確認して、実施を推奨しています。日本ではまだ賛否両論ありますが、アメリカを筆頭に欧米では虫歯予防の主流になっています。
最近の研究によって、フッ素には次の三つの働きによる虫歯予防効果があることが確認されています。
1.酸に対する抵抗力の強い丈夫な歯を作る
2.細菌に作用して虫歯の原因となる酸が作られるのを抑える
3.虫歯になりかけた歯の表面を元に戻す
歯が形成される時期にフッ素が作用すると、フッ素がエナメル質と結びついて歯を丈夫にし、酸に溶けにくい抵抗力のある歯質を作ります。また、歯が生えてくると、フッ素は細菌に作用して、虫歯の原因になる酸が作られるのを抑えます。
ただし、フッ素を塗っただけで虫歯予防ができるわけではありません。甘いおやつや飲み物など、糖分を取る回数を少なくする、ブラッシングをしっかり行う、歯科医院で定期健診を受ける、栄養バランスの整った食事など生活習慣に気をつける、などを心がけることが大切です。 -
そもそも、フッ素って?
-
フッ素は自然界に存在する元素のひとつです。
フッ素は体に必要な栄養素であり、ほとんどの食べ物や水に含まれています。
特に海産物やお茶には多くのフッ素が含まれており、欧米人に比べ日本人は2倍近く摂取していると言われています。 -
フッ素を使えば虫歯も治るの?
-
進行したむし歯は、フッ素だけでは治りません!
フッ素は初期のむし歯には有効ですが、すでに穴が空いていたり、痛みが出てきているようなむし歯はフッ素だけで治ることはありません。
できるだけ早く診察に来てください。
虫歯治療について
-
フッ素を使えば虫歯も治るの?
-
進行したむし歯は、フッ素だけでは治りません!
フッ素は初期のむし歯には有効ですが、すでに穴が空いていたり、痛みが出てきているようなむし歯はフッ素だけで治ることはありません。
できるだけ早く診察に来てください。 -
治療途中ですが、痛みが無くなった からもう通わなくても大丈夫?
-
菌が減ってくると痛みが消えてきますが、菌がいなくなったわけではありません。
再発を防ぐためにも最後まで通いましょう。 -
一度に治療は行なえないの?
-
できないわけではありませんが、何時間も口を開けたまま治療を受け続けることになります。
また、一度に行うと患部の周囲の組織にかなりの負担がかかりますので、お勧めできません。 -
神経が無いはずなのに治療中チクッとしたのですが?
-
チクッとしたのは器具の先が根の先端まで達したからです。
これは、歯の内部がきれいになり隅々まで掃除されたという証拠です。
安心してください。 -
治療後、腫れて痛くなったのですが?
-
菌の掃除と薬の刺激で炎症が一時的に起こり、何日間か痛むことがあります。
しかしこれは免疫反応の一つで、じきにおさまります。
装置について
-
保定装置とはどんなものですか?
-
矯正装置が外れると、今度は「リテーナー」という保定装置をつける場合があります。
矯正装置をつけ、歯の移動が終わったあとは、周囲の骨や歯肉がまだ歯となじんでいない可能性があり、とても不安定な状態です。そこでリテーナーを装着し、新しい歯の位置と骨、歯肉をなじませてしっかりと咬めるようにするのです。
矯正装置は歯を動かすための装置ですが、リテーナーは歯を動かさないようにするための装置といえます。
このリテーナーをつけていないと、元の歯並びやかみ合わせに戻ってしまう可能性があります。リテーナーは通常、矯正装置と同じくらいの装着期間が必要とされています。 -
矯正装置の影響で虫歯や歯周病になることはありますか?
-
矯正装置をつけていると食べ物のカスがたまり、虫歯が発生したり、歯周病になりやすくなることがあります。
これを防ぐために、食後には必ずハミガキをすることが大切です。
また、矯正装置にも汚れがたまっていることがあるので、装置もしっかりみがくようにしましょう。
診療日について
-
診療日・時間は?
-
診療日は平日と土曜日になります。
水・日・祝日は休診日です。(ただし、祝日のある週の水曜日は診療します)
診療時間は平日9:30~18:00、土曜日8:30~16:30です。
矯正治療の診療前のご相談も受け付けています。
0575-24-6900まで、お気軽にお電話ください。
食事について
-
矯正中でも、普通にごはんを食べて大丈夫ですか?
-
矯正中でも普通にごはんは食べられますが、避けたほうが良い食べ物はあります。
矯正装置をつけた後は痛みや違和感があることが多いので、やわらかいものを小さく切り、ゆっくりと食べるようにしましょう。装置に慣れてきたら、とくに心配はないと思います。
しかし、歯にくっつきやすいガムなどは避けたほうがいいでしょう。また、装置を傷つけてしまったり、破損する可能性があるので、硬い食べ物を食べる際は注意が必要です。