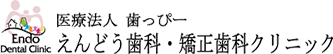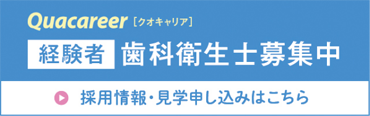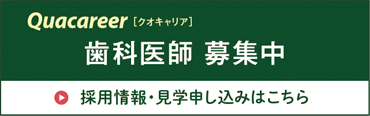歯周病について
皆様こんにちは!今月の歯の豆知識を担当させていただきます 歯科医師の池上昂秀です。
今回の歯の豆知識では歯周病についてのお話をさせていただきたいと思います。
例年に比べ全国的に降雪量が多く、寒い日が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか!
様々なことがあった2021年も終わり、新たに2022年がスタートしましたね!
年末年始をご家族と過ごされた方、ゆっくりとお休みを満喫された方、好きなことをされた方など、たくさんいらっしゃると思います。それから、年末年始は美味しい物を食べる機会も多いので、ついつい食べすぎてしまう方も多いのではないでしょうか。
新年、気持ちを新たに2022年も頑張っていきたいと思います。
先程、お話させていただいたように、美味しいものを美味しく食べるためにも、お口の中は健康な状態を長く保っていきたいですよね。
歯周病は、歯の周りの組織に炎症が起きてしまい、歯を支えてくれている組織が弱っていってしまう病気です。
最近では、歯周病と糖尿病、歯周病と認知症など、全身疾患との関係性が話題になって来ています。
そこで、歯周病とはどうのような病気なのか見ていきましょう。
・歯周病の主な原因
歯周病の主な原因はバイオフィルム(プラーク)と言われています。
歯石の表面はバイオフィルムを作り出す、かっこうの場所となるため、歯周病の発症・進行が促進されると言われています。
歯石により歯周組織の歯の根面への再付着が妨げられてしまうので、歯石を取り残すと歯周組織の修復が妨げられてしまうと考えられています。
 ・バイオフィルムの質
お口の中にどんな種類の歯周病菌がいるかによって、バイオフィルムの病原性が変わっていきます。バイオフィルムの病原性は磨き残しの量より、質(細菌種) で決まります。
それから、バイオフィルムの病原性は周囲の環境によって大きく影響を受けます。
細菌にとって、栄養環境が良くなるとバイオフィルムの病原性は上がります。
バイオフィルムが低病原性から高病原性に変化することはmicrobial shiftと呼ばれ、
歯周病の発症の原因は バイオフィルムのmicrobial shift と言われています。
・歯周病の病原菌
歯周病の病原菌はレッドコンプレックスと呼ばれる代表的な細菌だと言われています。
下記の3種類の菌がレッドコンプレックスに分類される病原菌です。
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Treponema denticola
・歯周病の始まり
歯と歯ぐきの間には歯周ポケットと呼ばれる隙間が存在します。その隙間に細菌が付着することでバイオフィルムが形成され、まず、歯肉炎が起きます。その状況でさらにポケットの奥深くに細菌が侵入していくことで歯周炎が起き、歯周病と呼ばる状態になっていきます。この状態になってしまうと歯を支えてくれている歯周組織に変化が起きてしまうのです。
・歯周病の予防
歯周病を予防する方法として、
毎日の歯磨きと歯科医院での定期検診、歯のお手入れが大切です。
毎日の歯磨きで、歯と歯ぐきの間のバイオフィルム(プラーク)の付着を取り除きます。
また、定期的に歯科医院で歯ぐきの検査をし、超音波スケーリングをすることで、バイオフィルムを除去することができ、歯周病の予防につながると考えられます。
・バイオフィルムの質
お口の中にどんな種類の歯周病菌がいるかによって、バイオフィルムの病原性が変わっていきます。バイオフィルムの病原性は磨き残しの量より、質(細菌種) で決まります。
それから、バイオフィルムの病原性は周囲の環境によって大きく影響を受けます。
細菌にとって、栄養環境が良くなるとバイオフィルムの病原性は上がります。
バイオフィルムが低病原性から高病原性に変化することはmicrobial shiftと呼ばれ、
歯周病の発症の原因は バイオフィルムのmicrobial shift と言われています。
・歯周病の病原菌
歯周病の病原菌はレッドコンプレックスと呼ばれる代表的な細菌だと言われています。
下記の3種類の菌がレッドコンプレックスに分類される病原菌です。
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Treponema denticola
・歯周病の始まり
歯と歯ぐきの間には歯周ポケットと呼ばれる隙間が存在します。その隙間に細菌が付着することでバイオフィルムが形成され、まず、歯肉炎が起きます。その状況でさらにポケットの奥深くに細菌が侵入していくことで歯周炎が起き、歯周病と呼ばる状態になっていきます。この状態になってしまうと歯を支えてくれている歯周組織に変化が起きてしまうのです。
・歯周病の予防
歯周病を予防する方法として、
毎日の歯磨きと歯科医院での定期検診、歯のお手入れが大切です。
毎日の歯磨きで、歯と歯ぐきの間のバイオフィルム(プラーク)の付着を取り除きます。
また、定期的に歯科医院で歯ぐきの検査をし、超音波スケーリングをすることで、バイオフィルムを除去することができ、歯周病の予防につながると考えられます。
 ・まとめ
今回は簡単ではございますが、5つの項目に分けて、お話させていただきました。歯周病の病原菌の名前を挙げさせていただきましたが、当医院ではお口の中に歯周病の病原菌がどの程度存在するかを検査することができる機械をご用意しております。ご質問などございましたら、お気軽にお声かけ下さい。
参考文献 ) 21世紀のペリオドントロジーダイジェスト クインテッセンス出版
・まとめ
今回は簡単ではございますが、5つの項目に分けて、お話させていただきました。歯周病の病原菌の名前を挙げさせていただきましたが、当医院ではお口の中に歯周病の病原菌がどの程度存在するかを検査することができる機械をご用意しております。ご質問などございましたら、お気軽にお声かけ下さい。
参考文献 ) 21世紀のペリオドントロジーダイジェスト クインテッセンス出版
 ・バイオフィルムの質
お口の中にどんな種類の歯周病菌がいるかによって、バイオフィルムの病原性が変わっていきます。バイオフィルムの病原性は磨き残しの量より、質(細菌種) で決まります。
それから、バイオフィルムの病原性は周囲の環境によって大きく影響を受けます。
細菌にとって、栄養環境が良くなるとバイオフィルムの病原性は上がります。
バイオフィルムが低病原性から高病原性に変化することはmicrobial shiftと呼ばれ、
歯周病の発症の原因は バイオフィルムのmicrobial shift と言われています。
・歯周病の病原菌
歯周病の病原菌はレッドコンプレックスと呼ばれる代表的な細菌だと言われています。
下記の3種類の菌がレッドコンプレックスに分類される病原菌です。
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Treponema denticola
・歯周病の始まり
歯と歯ぐきの間には歯周ポケットと呼ばれる隙間が存在します。その隙間に細菌が付着することでバイオフィルムが形成され、まず、歯肉炎が起きます。その状況でさらにポケットの奥深くに細菌が侵入していくことで歯周炎が起き、歯周病と呼ばる状態になっていきます。この状態になってしまうと歯を支えてくれている歯周組織に変化が起きてしまうのです。
・歯周病の予防
歯周病を予防する方法として、
毎日の歯磨きと歯科医院での定期検診、歯のお手入れが大切です。
毎日の歯磨きで、歯と歯ぐきの間のバイオフィルム(プラーク)の付着を取り除きます。
また、定期的に歯科医院で歯ぐきの検査をし、超音波スケーリングをすることで、バイオフィルムを除去することができ、歯周病の予防につながると考えられます。
・バイオフィルムの質
お口の中にどんな種類の歯周病菌がいるかによって、バイオフィルムの病原性が変わっていきます。バイオフィルムの病原性は磨き残しの量より、質(細菌種) で決まります。
それから、バイオフィルムの病原性は周囲の環境によって大きく影響を受けます。
細菌にとって、栄養環境が良くなるとバイオフィルムの病原性は上がります。
バイオフィルムが低病原性から高病原性に変化することはmicrobial shiftと呼ばれ、
歯周病の発症の原因は バイオフィルムのmicrobial shift と言われています。
・歯周病の病原菌
歯周病の病原菌はレッドコンプレックスと呼ばれる代表的な細菌だと言われています。
下記の3種類の菌がレッドコンプレックスに分類される病原菌です。
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Treponema denticola
・歯周病の始まり
歯と歯ぐきの間には歯周ポケットと呼ばれる隙間が存在します。その隙間に細菌が付着することでバイオフィルムが形成され、まず、歯肉炎が起きます。その状況でさらにポケットの奥深くに細菌が侵入していくことで歯周炎が起き、歯周病と呼ばる状態になっていきます。この状態になってしまうと歯を支えてくれている歯周組織に変化が起きてしまうのです。
・歯周病の予防
歯周病を予防する方法として、
毎日の歯磨きと歯科医院での定期検診、歯のお手入れが大切です。
毎日の歯磨きで、歯と歯ぐきの間のバイオフィルム(プラーク)の付着を取り除きます。
また、定期的に歯科医院で歯ぐきの検査をし、超音波スケーリングをすることで、バイオフィルムを除去することができ、歯周病の予防につながると考えられます。
 ・まとめ
今回は簡単ではございますが、5つの項目に分けて、お話させていただきました。歯周病の病原菌の名前を挙げさせていただきましたが、当医院ではお口の中に歯周病の病原菌がどの程度存在するかを検査することができる機械をご用意しております。ご質問などございましたら、お気軽にお声かけ下さい。
参考文献 ) 21世紀のペリオドントロジーダイジェスト クインテッセンス出版
・まとめ
今回は簡単ではございますが、5つの項目に分けて、お話させていただきました。歯周病の病原菌の名前を挙げさせていただきましたが、当医院ではお口の中に歯周病の病原菌がどの程度存在するかを検査することができる機械をご用意しております。ご質問などございましたら、お気軽にお声かけ下さい。
参考文献 ) 21世紀のペリオドントロジーダイジェスト クインテッセンス出版