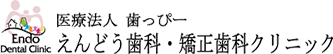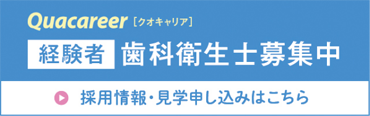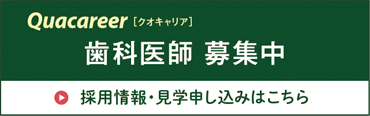忘れていませんか?インプラントのメインテナンス
こんにちは。歯科助手の福井です。
最近、当院の衛生士さんにお口の中を見てもらいお掃除をしてもらったところ、人生初の虫歯が見つかりました!ショックでしたが、小さい虫歯だったのですぐに先生に治療してもらい、一日で虫歯治療が完了しました。定期的にお口の中を見てもらい早期発見、治療の大切さがわかりました。今日はインプラントをいれたあとの定期健診の大切さについてお話します。
失った歯に変わる補綴物は入れ歯、ブリッジ、インプラントと三つあります。今日は3つの選択肢の中の一つである「インプラント」のメンテナンスのお話をしていきます。
インプラントは「固定式なので入れ歯のような違和感がなく食事ができる」「審美性が高い」など評判ではあるものの「グラグラする」「抜けてしまった」というトラブルも、もちろんあります。インプラントを失う原因には、インプラントの歯周病である「インプラント歯周炎」や、過剰な噛む力がかかったことによるインプラントの脱落などがあります。
そういったトラブルを未然に防ぐためには歯科医院での定期的なメンテナンスと、レベルの高いセルフケアが欠かせません。インプラントをできるだけ長持ちさせるために大切なことを紹介していきます!
歯科医院ではインプラント治療を行う際に、治療後も定期健診に通っていただくように説明をしています。しかし入れてから何年か経つと痛みや違和感がないからといった理由でしばらく定期健診をお休みしてしまう患者さんも多くいます。
インプラントは、目に見えている噛む部分から歯の根っこにあたる部分まで完全に人工物ですのでインプラント自体は細菌に強いです。ですが、インプラントが埋まっている周りの歯ぐきは天然の歯と同じように歯周病になるリスクはあります!これをインプラント周囲炎といいます。他には噛む力が強い方など、噛む力を受け止めるうちにネジがゆるんだり人工歯が欠けたり、インプラント自体がダメージを受けることもあります。
みなさんが違和感や痛みを感じてから来院していただいても対応が難しい場合が多く、最悪の場合インプラントが抜けてしまうことになる場合もあります。
インプラントは保険がきかないので自費治療になります。健康のためにお金をかけて入れたインプラントを長持ちさせるには日々のケアがしっかりできているかチェックすることや健康状態を確認するのはインプラントを長持ちさせるには不可欠です。
ではインプラントと天然歯は何が違うのか説明していきます。
天然歯では、歯茎の内部に繊維がのびていて、歯と密着に絡みついています。これは歯と歯茎の付着を強化する。体内への細菌の侵入を防ぐバリアの役目などがあります。
歯を失えば、この繊維もいっしょに失われます。なのでインプラントまわりの歯茎は細菌に弱く、歯周病になりやすいのです!
更に、天然歯には、歯の根っことあごの骨の間に「歯根膜」と呼ばれる厚さ0.5mmほどの薄い組織があります。この歯根膜が歯の根と顎の骨を強固に結び付けています。
歯根膜は歯の根っこと顎の骨のあいだにあるクッションのようなもので、かんだときにさまざまな方向から生じる力を吸収・分散させ過剰な力が加わらないようにしてくれています。また、かんだときに硬さや、感触を感知して無意識下で噛む力を調節してくれる機能もあります。
しかし、インプラントはインプラント体のチタンとあごの骨が直接結合しています。
クッションやセンサー機能がないので、過剰な力がによりトラブルがおきやすいのです。
ではインプラントの歯周病はどのように進行するのでしょうか?
天然歯に起こる歯周病とインプラントに起こる歯周病の犯人はどちらもプラークが原因です。
インプラントの歯周病はインプラントに付着したプラークが周りの歯ぐきを炎症させて、腫れや出血を起こします。これは専門的には「インプラント周囲粘膜炎」といいます。
そして、それが悪化すると、あごの骨にも炎症が及ぶインプラントの歯周病=「インプラント周囲炎」となります。
歯周炎が進むと最終的には骨が失われてインプラントは抜けてしまいます。
実はインプラントのほうが歯周病には弱いのです。
普通の歯周病では顎の骨が失われる点は共通していますが、歯周病では炎症は骨には及んでいません。炎症と骨の間には常に歯ぐきがあって、細菌が骨の内部に入り込まないように防波堤となっています(骨の消失にあわせて歯ぐきも下がっていきます。)
しかし、インプラント周囲炎では骨の内部に細菌が入り込んで炎症がおきています。