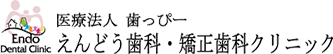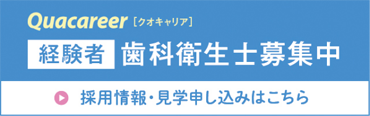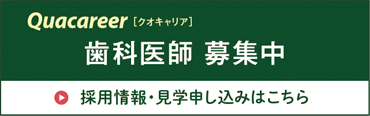喫煙は口の中にどんな影響があるのか
皆さんこんにちは、歯科衛生士の河合です。
今回は喫煙が口腔や歯周組織にどのような影響を与えるのかについてお話しさせていただきます。
皆さんは、日本の喫煙人口はどれくらいか知っていますか?
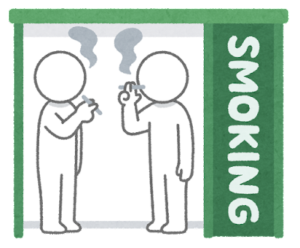 平成29年国民健康・栄養調査の結果では、
現在習慣的に喫煙している人の割合は、総数17.7% 男性29.4% 女性7.2%となっています。
厚生労働省では、健康日本21において、
生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を基本的な方針の柱の1つとして位置づけ、
生活習慣病の重大な危険因子である喫煙による健康被害を短期的ならびに中期的に減少させるため、
『喫煙をやめたい人がやめる』ことを数値化した成人喫煙率12%の数値目標を設定して取り組みを進めています。
また、健康増進法の一部を改正する法律では、受動喫煙対策を定め、
望まない受動喫煙の防止を図ることとしています。
たばこの煙に含まれるニコチンやタールなどの化学物質は、
喫煙者本人はもちろんのこと、喫煙をしていない周囲の人々にも影響を及ぼしてしまいます。
平成29年国民健康・栄養調査の結果では、
現在習慣的に喫煙している人の割合は、総数17.7% 男性29.4% 女性7.2%となっています。
厚生労働省では、健康日本21において、
生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を基本的な方針の柱の1つとして位置づけ、
生活習慣病の重大な危険因子である喫煙による健康被害を短期的ならびに中期的に減少させるため、
『喫煙をやめたい人がやめる』ことを数値化した成人喫煙率12%の数値目標を設定して取り組みを進めています。
また、健康増進法の一部を改正する法律では、受動喫煙対策を定め、
望まない受動喫煙の防止を図ることとしています。
たばこの煙に含まれるニコチンやタールなどの化学物質は、
喫煙者本人はもちろんのこと、喫煙をしていない周囲の人々にも影響を及ぼしてしまいます。
 肺がんを代表とする呼吸器疾患、循環器疾患や消化器疾患などの全身疾患だけではなく、
口腔がんや歯周病の発症にも深い関わりがあります。
肺がんを代表とする呼吸器疾患、循環器疾患や消化器疾患などの全身疾患だけではなく、
口腔がんや歯周病の発症にも深い関わりがあります。
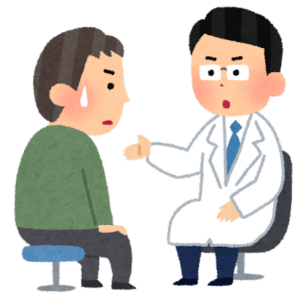 では、ここで具体的に口腔や歯周組織にどのようなリスクがあるのかお話しさせていただきます。
タバコの煙と接触する歯肉や口腔粘膜は、皮膚と同じように、重曹扁平上皮という上皮で覆われていますが、
タバコの煙の影響は、上皮の厚さやその直下の粘膜下組織に分布する、血管の分布度に依存します。
特に、口腔粘膜は、物質透過性が高く、タバコの影響をとても受けやすいです。
喫煙直後は、ニコチンの血管を収縮する作用によって、
歯肉上皮下毛細血管網の血流量の減少やヘモグロビン量および酸素飽和度の低下を起こします。
そして、長期間の喫煙習慣により、逆に炎症が起きていても、歯肉出血が減少してしまいます。
そのため、歯周ポケットが深く進行した歯周炎であっても歯茎の検査をした際に出血が少なく、
歯肉のメラニン色素沈着(歯肉の赤黒い着色)もあり、歯肉の炎症症状が分かりにくくなってしまいます。
では、ここで具体的に口腔や歯周組織にどのようなリスクがあるのかお話しさせていただきます。
タバコの煙と接触する歯肉や口腔粘膜は、皮膚と同じように、重曹扁平上皮という上皮で覆われていますが、
タバコの煙の影響は、上皮の厚さやその直下の粘膜下組織に分布する、血管の分布度に依存します。
特に、口腔粘膜は、物質透過性が高く、タバコの影響をとても受けやすいです。
喫煙直後は、ニコチンの血管を収縮する作用によって、
歯肉上皮下毛細血管網の血流量の減少やヘモグロビン量および酸素飽和度の低下を起こします。
そして、長期間の喫煙習慣により、逆に炎症が起きていても、歯肉出血が減少してしまいます。
そのため、歯周ポケットが深く進行した歯周炎であっても歯茎の検査をした際に出血が少なく、
歯肉のメラニン色素沈着(歯肉の赤黒い着色)もあり、歯肉の炎症症状が分かりにくくなってしまいます。
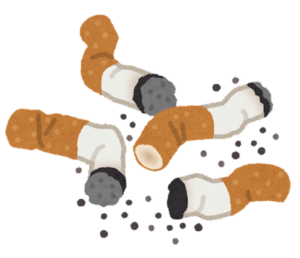 〈喫煙している歯肉炎、歯周炎患者の臨床所見〉
喫煙関連歯肉炎
・肉眼的所見:歯肉のメラニン色素沈着の頻度増加
・臨床検査所見:歯肉炎症やプロービング時の歯肉出血の低下
喫煙関連歯周炎
・肉眼的所見:歯肉辺縁部の線維性肥厚(歯茎がゴツゴツした感じになること)歯肉とメラニン色素沈着の頻度増加、歯面の着色
・臨床検査所見:歯周ポケット・歯槽骨吸収の悪化、プロービング時の歯肉出血の低下
・臨床検査結果:重度な歯周炎の頻度増加プラーク・歯石の沈着量と病態が一致しない
このように
喫煙によって、本来の歯周組織の状態が分かりにくくなり気づいた時には、
歯周病が進行している恐れがあります。
〈喫煙している歯肉炎、歯周炎患者の臨床所見〉
喫煙関連歯肉炎
・肉眼的所見:歯肉のメラニン色素沈着の頻度増加
・臨床検査所見:歯肉炎症やプロービング時の歯肉出血の低下
喫煙関連歯周炎
・肉眼的所見:歯肉辺縁部の線維性肥厚(歯茎がゴツゴツした感じになること)歯肉とメラニン色素沈着の頻度増加、歯面の着色
・臨床検査所見:歯周ポケット・歯槽骨吸収の悪化、プロービング時の歯肉出血の低下
・臨床検査結果:重度な歯周炎の頻度増加プラーク・歯石の沈着量と病態が一致しない
このように
喫煙によって、本来の歯周組織の状態が分かりにくくなり気づいた時には、
歯周病が進行している恐れがあります。
 全身の健康だけではなく、口腔の健康のためにも早期の禁煙をお勧めします。
また、定期検診を大切にして早期発見に繋げましょう。
全身の健康だけではなく、口腔の健康のためにも早期の禁煙をお勧めします。
また、定期検診を大切にして早期発見に繋げましょう。
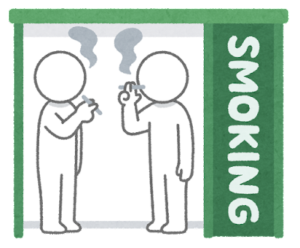 平成29年国民健康・栄養調査の結果では、
現在習慣的に喫煙している人の割合は、総数17.7% 男性29.4% 女性7.2%となっています。
厚生労働省では、健康日本21において、
生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を基本的な方針の柱の1つとして位置づけ、
生活習慣病の重大な危険因子である喫煙による健康被害を短期的ならびに中期的に減少させるため、
『喫煙をやめたい人がやめる』ことを数値化した成人喫煙率12%の数値目標を設定して取り組みを進めています。
また、健康増進法の一部を改正する法律では、受動喫煙対策を定め、
望まない受動喫煙の防止を図ることとしています。
たばこの煙に含まれるニコチンやタールなどの化学物質は、
喫煙者本人はもちろんのこと、喫煙をしていない周囲の人々にも影響を及ぼしてしまいます。
平成29年国民健康・栄養調査の結果では、
現在習慣的に喫煙している人の割合は、総数17.7% 男性29.4% 女性7.2%となっています。
厚生労働省では、健康日本21において、
生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を基本的な方針の柱の1つとして位置づけ、
生活習慣病の重大な危険因子である喫煙による健康被害を短期的ならびに中期的に減少させるため、
『喫煙をやめたい人がやめる』ことを数値化した成人喫煙率12%の数値目標を設定して取り組みを進めています。
また、健康増進法の一部を改正する法律では、受動喫煙対策を定め、
望まない受動喫煙の防止を図ることとしています。
たばこの煙に含まれるニコチンやタールなどの化学物質は、
喫煙者本人はもちろんのこと、喫煙をしていない周囲の人々にも影響を及ぼしてしまいます。
 肺がんを代表とする呼吸器疾患、循環器疾患や消化器疾患などの全身疾患だけではなく、
口腔がんや歯周病の発症にも深い関わりがあります。
肺がんを代表とする呼吸器疾患、循環器疾患や消化器疾患などの全身疾患だけではなく、
口腔がんや歯周病の発症にも深い関わりがあります。
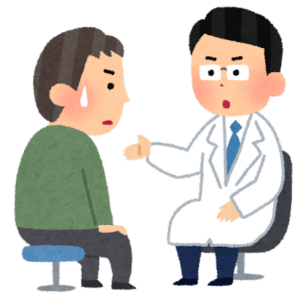 では、ここで具体的に口腔や歯周組織にどのようなリスクがあるのかお話しさせていただきます。
タバコの煙と接触する歯肉や口腔粘膜は、皮膚と同じように、重曹扁平上皮という上皮で覆われていますが、
タバコの煙の影響は、上皮の厚さやその直下の粘膜下組織に分布する、血管の分布度に依存します。
特に、口腔粘膜は、物質透過性が高く、タバコの影響をとても受けやすいです。
喫煙直後は、ニコチンの血管を収縮する作用によって、
歯肉上皮下毛細血管網の血流量の減少やヘモグロビン量および酸素飽和度の低下を起こします。
そして、長期間の喫煙習慣により、逆に炎症が起きていても、歯肉出血が減少してしまいます。
そのため、歯周ポケットが深く進行した歯周炎であっても歯茎の検査をした際に出血が少なく、
歯肉のメラニン色素沈着(歯肉の赤黒い着色)もあり、歯肉の炎症症状が分かりにくくなってしまいます。
では、ここで具体的に口腔や歯周組織にどのようなリスクがあるのかお話しさせていただきます。
タバコの煙と接触する歯肉や口腔粘膜は、皮膚と同じように、重曹扁平上皮という上皮で覆われていますが、
タバコの煙の影響は、上皮の厚さやその直下の粘膜下組織に分布する、血管の分布度に依存します。
特に、口腔粘膜は、物質透過性が高く、タバコの影響をとても受けやすいです。
喫煙直後は、ニコチンの血管を収縮する作用によって、
歯肉上皮下毛細血管網の血流量の減少やヘモグロビン量および酸素飽和度の低下を起こします。
そして、長期間の喫煙習慣により、逆に炎症が起きていても、歯肉出血が減少してしまいます。
そのため、歯周ポケットが深く進行した歯周炎であっても歯茎の検査をした際に出血が少なく、
歯肉のメラニン色素沈着(歯肉の赤黒い着色)もあり、歯肉の炎症症状が分かりにくくなってしまいます。
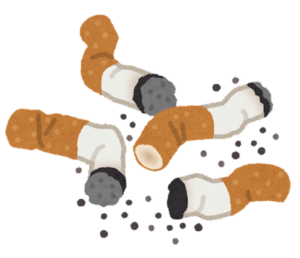 〈喫煙している歯肉炎、歯周炎患者の臨床所見〉
喫煙関連歯肉炎
・肉眼的所見:歯肉のメラニン色素沈着の頻度増加
・臨床検査所見:歯肉炎症やプロービング時の歯肉出血の低下
喫煙関連歯周炎
・肉眼的所見:歯肉辺縁部の線維性肥厚(歯茎がゴツゴツした感じになること)歯肉とメラニン色素沈着の頻度増加、歯面の着色
・臨床検査所見:歯周ポケット・歯槽骨吸収の悪化、プロービング時の歯肉出血の低下
・臨床検査結果:重度な歯周炎の頻度増加プラーク・歯石の沈着量と病態が一致しない
このように
喫煙によって、本来の歯周組織の状態が分かりにくくなり気づいた時には、
歯周病が進行している恐れがあります。
〈喫煙している歯肉炎、歯周炎患者の臨床所見〉
喫煙関連歯肉炎
・肉眼的所見:歯肉のメラニン色素沈着の頻度増加
・臨床検査所見:歯肉炎症やプロービング時の歯肉出血の低下
喫煙関連歯周炎
・肉眼的所見:歯肉辺縁部の線維性肥厚(歯茎がゴツゴツした感じになること)歯肉とメラニン色素沈着の頻度増加、歯面の着色
・臨床検査所見:歯周ポケット・歯槽骨吸収の悪化、プロービング時の歯肉出血の低下
・臨床検査結果:重度な歯周炎の頻度増加プラーク・歯石の沈着量と病態が一致しない
このように
喫煙によって、本来の歯周組織の状態が分かりにくくなり気づいた時には、
歯周病が進行している恐れがあります。
 全身の健康だけではなく、口腔の健康のためにも早期の禁煙をお勧めします。
また、定期検診を大切にして早期発見に繋げましょう。
全身の健康だけではなく、口腔の健康のためにも早期の禁煙をお勧めします。
また、定期検診を大切にして早期発見に繋げましょう。